
石神地区で梅の栽培が始まったのは江戸時代。日照時間の長さ、気温の寒暖差、水はけの良さ、多くのミネラルを含む黒潮の風、それを受け止める標高400メートルの大蛇峰と、良い梅を生み、育てるための条件が揃っていました。まさに、梅に愛される土地だったのです。
梅の収穫は毎年6月にスタート。枝からもぎとるのではなく、自然に落下したものだけを毎日人の手で拾うため、収穫期には地面に網を敷き詰めて果実を受け止めています。
洗浄、選別を経た梅たちは塩漬けの工程へ。天候や梅の水分を見極めて、職人たちが塩を加減します。
梅雨が明ける頃、梅たちは太陽の下に出てきて、約一週間にわたる天日星へ。
まんべんなく陽光があたるよう、一粒ずつ手作業で裏返していきます。
その後、梅干は各々の質にあった味付けを施され、皆様の元に。
自然の恩恵だけに頼ることなく、私たちもまた、梅を愛する者として、日々精進してまいります。
会社概要

紀州石神邑は地域古来の伝統のすばらしさを大切にしています。
また、現代人が今必要としている「安心」と「安全」も 大切にしています。あらゆる梅商品に対して、従来の品質を維持しながらも、
お客様の声をしっかりと受け止め、改善していく勇気を大切にしています。
| 社名 | 株式会社石神邑 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 濱田朝康 |
| 創立年月 | 平成4年8月 |
| 事業内容 | 紀州梅干、梅酒、梅関連製品の通信販売 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒646-0101 和歌山県田辺市上芳養391番地 |
| 電話番号 | フリーダイヤル0120-37-0107 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行田辺支店 紀陽銀行田辺支店 |
| 関連グループ | 株式会社濱田農園(自社農園) 株式会社濱田(製造・卸) 株式会社石神邑(通信販売) |
沿革
-
1180年頃平安時代
源平合戦で敗れた平家の落ち武者、録部と宮ノ谷に住んでいた鎮守姫が石神に 住み着き、現在の石神の基を築く。石神邑こぼれ話1.「石神伝説」
-
1600年頃江戸時代
梅の租税が免除され紀州で梅栽培が盛んに行われるようになる。 濱田の先祖もウバメガシを伐採し、備長炭をつくりながら、梅栽培に力をいれる ようになる。
-
1889年頃明治時代
明治の大水害によって、石神地区にある大蛇峰が崩落。 崩落した山肌に梅を植え、本格的な梅栽培が開始される。
-
1913年大正2年
濱田武次郎が梅畑を相続する。 濱田武次郎が塩漬けにした梅を木樽に詰め築地市場へ販売を開始。
-
1963年昭和38年
-
1981年昭和56年
現、会長の濱田洋が調味梅干の製造販売を開始する。
-
1992年平成4年
株式会社石神邑(通信販売会社)を設立。
-
1997年平成9年
石神梅林を紀州石神田辺梅林と改名。
-
2006年平成18年
梅酒の製造販売開始。
-
2007年平成19年
パイロットファーム完成。これまで急斜面で作業性の悪かった梅畑を山を崩し、 谷を埋立て、平坦な梅畑を造成。これにより作業効率が急激に上昇。 総事業費13億5000万円・受益面積28.4ha・圃場面関24ha・水路兼用道路 4000m・排水路工2000m
その昔、石神の奥にある宮ノ谷に住んでいた鎮守姫。戦に敗れ逃れてきた平家の武士、録部を介抱した事がきっかけとなり、二人は結ばれました。先に逝った鎮守姫の為に墓を建て供養した録部にもついに天のお迎えが。その時「わしを祀って石神鎮守草別大明神と唱えてくれ そうすればこの土地が繁栄するよう守る」と言い残しこの世を去りました。現在でもその祠は残され、石神地域を二人が見守り続けてくれています。
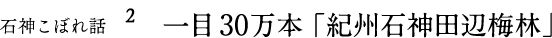
江戸時代から梅栽培が行われている石神地区は標高400mの大蛇峰をはじめとする山々に囲まれたたった13世帯の集落です。明治22年の大水害では大蛇峰がまるで半分に割れたように大崩落しました。その山肌に梅の木を植えたのが梅林のはじまりです。 黒潮の程よい潮風、水はけの良い土壌、惜しみなく降り注ぐ太陽。梅に選ばれたとしか言いようのない奇跡的な環境で代々梅栽培を生業として生活しています。

アクセス
電車でお越しの場合
最寄り駅:紀勢本線 紀伊田辺駅
紀伊田辺駅下車後、タクシーなど車で約20分。
自動車でお越しの場合
阪和自動車道南紀田辺ICを降りてすぐ左側道に入り最初の信号を左折、県道208号を北上。
南紀田辺ICより約15分。

